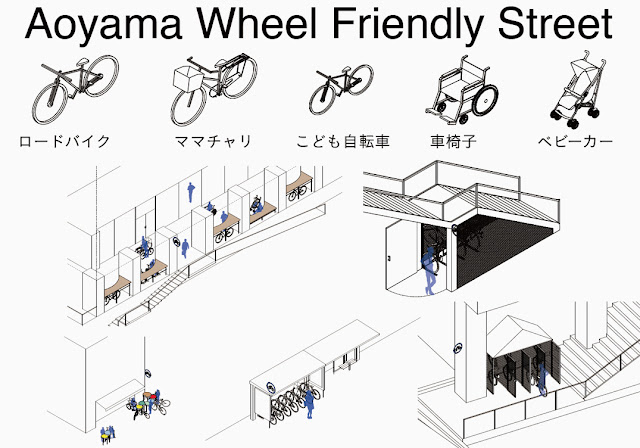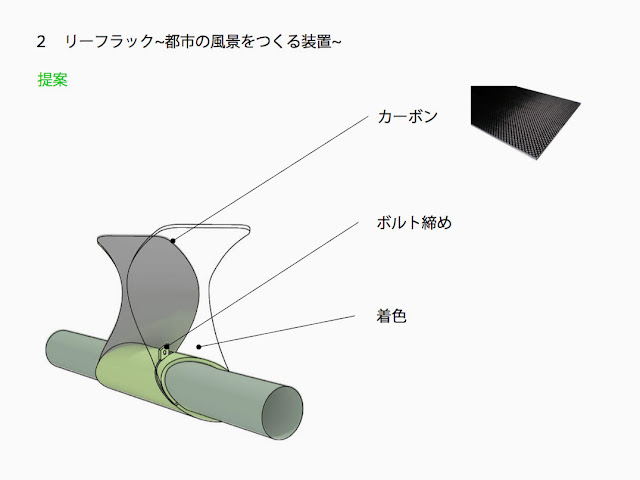1〜2階が吹き抜けの駐車場の小さな雑居ビル。3階に観葉植物が見えるのがオフィスだ。

ご存じの方も多いかと思うが遠藤さんは「大阪新美術館」の設計をコンペにより2017年2月に勝ち取った。東京品川にオフィスを構えているが、この仕事のためにスタッフの殆どと共に大阪に移り住み、大阪オフィスを立ち上げた。関東の業務や、他の業務の多くもここ大阪で進行させている。

大阪新美術館計画地(Googleマップより)。中之島の一番幅が広くなる辺りで、東(左)に関西電力本店ビル、南(上)に国立国際美術館、大阪市立科学館、西(右)は空地で大学の校舎が建つ予定。
関電ビル公開空地側から。右に見えている植栽の上に途切れたブリッジがあるが、美術館を造る造らないなどと検討している頃から、いつか接続できるようにと待ち構えている。このブリッジはコンペの要項にも記されていたそうだ。


西側は不測だが、各方向に大阪の異なる風景を切り取ることができる大開口。その大開口が光のトンネル(パサージュ)のように街の新しい風景をつくり出す。光のトンネルを強調するには外壁を白か黒にしたいが、街のなかにあって埋没しないように黒を選択し、新しいアイコンのような存在を目指す。内部はパサージュ空間を中心としながら空間体験を重ねながら巡れるようにする。
外壁の素材はオフィスで見せてもらったが、様々な素材と様々な黒を検討中だ。
構造は佐藤淳、照明はシリウス、ランドスケープはスタジオテラが担当している。

もうじき基本設計を完了させるスケジュールのため検討は大詰め。最新模型の詳細は今は公開できない。

美術館業務と、通常業務、新しいコンペと「ちょっと忙しすぎるな、、、(笑)。でも徹夜はさせない。早く帰って早く出社してもらっている、はず。」とフロアを見返す遠藤さん。

各地から手伝いに来てくれるインターン含め10数人が働くが、まだまだ人手が欲しいそうなので、社員、アルバイト、インターン共に募集中だそうだ。

軽井沢で計画中の別荘。尾根に建ち三方に傾斜する敷地。

大阪から軽井沢へは東京周りになるそうだ。

遠藤克彦さん。「このところ週1〜2が東京、すっかりメインは大阪。一番気をつけているのは体調管理です。」「延床20,000m2以上ある上、美術館は通常のビルの常識が通用せず、当たり前にできるはずのことがNGだったり、設備が異常に多いなど検討事項は無限とも思えるほどありますが、きっと素晴らしい建築にしますので期待していて下さい。」
竣工は2021年、4年半後の予定。
【大阪新美術館の公募型設計競技について】
***************************
japan-architects.com
日本の建築家・デザイナーと世界をリンク
Web : www.japan-architects.com
Twitter : @JapanArchitects
Twitter : @JapanArchitects